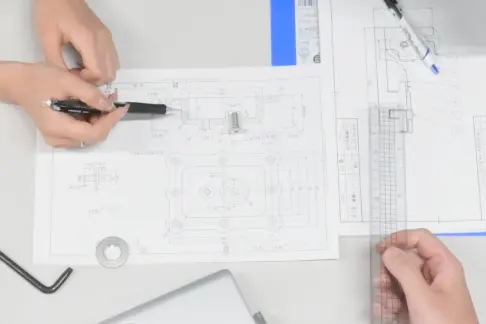解体分析エキスパート 第3回:電子レンジの解体分析
こんにちは!
「解体分析エキスパート」第3回をお届けします。今回は予告通り、家庭でおなじみの調理家電「電子レンジ」の解体分析を行いました。比較対象としたのは、同一メーカーによる2002年製と2019年製の単機能電子レンジ。およそ17年の開きがあるこの2台には、どのような違いがあるのでしょうか。特に注目したのは、使用されている締結部品の仕様です。


家庭用調理家電の特徴と設計要件
電子レンジは、高温・高電圧が発生する調理家電であり、内部にはマグネトロン、高電圧トランス、ファンモーターなど、多種多様な部品が集積されています。これらの部品を確実に固定し、安全性や耐久性を確保するためには、締結部品の選定と配置が極めて重要な要素となります。
今回の解体を通じて、2002年製と2019年製の製品には、以下のような明確な違いも見られました。


注目ポイント①:表面処理の変化 ― 六価クロムから三価クロムへ
最も大きな違いは、締結部品に施された表面処理です。
2002年製電子レンジ:締結部品に六価クロムめっきが使用されていました。これは防錆性能が高く、長年にわたり広く用いられてきた処理ですが、環境負荷や人体への影響が問題視されています。

2019年製電子レンジ:六価クロムに代わり、三価クロムめっきが主に使用されていました。これは、EUで施行されたRoHS指令(2006年7月1日施行)など、電気・電子機器における有害物質の含有を制限する環境規制への対応と、より持続可能な製品設計への移行を背景としていると考えられます。この変化は、サステナビリティや規制対応が製品設計に直結する時代への移行を象徴しています。

注目ポイント②:締結点数と配置の最適化
締結部品の点数は、2002年製が約51点、2019年製が約48点と、いずれも比較的シンプルな構成でした。2019年製では3点減少しており、締結部品の少量化が進んでいたのが印象的です。


注目ポイント③:締結部品の種類
両機種とも、ねじの頭部形状はすべて十字穴で、サイズはM3~M4、長さ6~12mmが中心でした。同一ねじの使い回しによる組立効率の向上や管理の簡素化が図られており、製造コストや整備性の向上に貢献していると考えられます。
2002年製では最大M5・長さ15mmのねじも使用されていましたが、2019年製では最大M4・長さ12mmまでに統一されていました。どちらの製品でも最も多く使われていたのはM4ねじで、強度設計と軽量化を意識した構成といえます。
特に、両機種で最も使用頻度が高かったのはM4x8の薄板用トラスタッピングねじでした。これは電子レンジの筐体である薄板に対し、片側から締付けが可能で、先端が尖っており、下穴の位置決めガイドや、ねじの喰いつきを良くする効果があります。塑性変形(フォーミング)によりめねじを形成し、ガタつきのない嵌合が得られるため、小ねじと比較してゆるみにくいと考えられます。

また、両機種とも、使用されていたねじの半数以上が「タップタイト(DIN7500)」でした。これはねじ胴部の断面が三角形(おにぎり形状)になっており、一般的なタッピンねじよりもねじ込みトルクが低く、高い締付け力と耐振性が得られるのが特徴です。繰り返しの使用にも強く、ねじバカになりにくい点も評価できます。

さらに、頭部下にセレーション付きワッシャーや歯付き・スプリングワッシャーなどの使用も見られました。

上記の締結部品の使用の目的と背景は以下の理由から、ゆるみにくい締結構造が採用されていると思われます:
(ア) 安全性の確保:電子レンジにはマグネトロンやトランスといった高電圧部品、ヒーターや冷却ファンといった高温部品が搭載されています。締結部が緩むと、ショート・発火・感電などの重大な事故につながる恐れがあるため、確実な固定が求められます。
(イ) 振動や熱によるゆるみ対策:ターンテーブルの回転や冷却ファンの動作により、微小な振動が常時発生します。また、加熱と冷却を繰り返すことで材料が膨張・収縮し、ねじに緩み力が加わります。これを防ぐため、耐振動性・耐熱性に優れた構造が必要です。
(ウ) 製品寿命と品質の維持:締結部品が緩むことで異音、部品の脱落、誤作動などの不具合が生じる恐れがあります。ゆるみにくい設計によって長期間の使用でも安定した性能を保ち、製品の信頼性を向上させることが可能になります。


解体結果と考察:時代とともに進化する締結設計
今回の解体分析からは、環境規制(RoHS指令)への明確な対応、そして製造効率・整備性・信頼性を重視した締結部品設計の進化が読み取れました。
特に、以下のような改善提案が考えられます:
締結部品の統一化の推進:ねじの種類やサイズをさらに統一することで、在庫・製造管理の効率化が期待できます。
まとめ
電子レンジのような調理家電では、耐熱・耐食・絶縁・安全性など、幅広い要求に応える締結部品設計が求められます。特に近年は、環境に配慮した材料・処理の選定が急速に進んでいることが明らかになりました。
このような知見は、家電製品の開発に携わる設計者や部品選定担当者にとって、今後の設計・調達方針を見直すうえで貴重なヒントになるはずです。
次回予告:カーナビゲーションの解体分析
次回は、電子レンジより複雑な構造を持つカーナビゲーションを解体・分析する予定です。どのような締結部品が使われ、どのような設計思想が反映されているのか? ぜひ次回もお楽しみに!