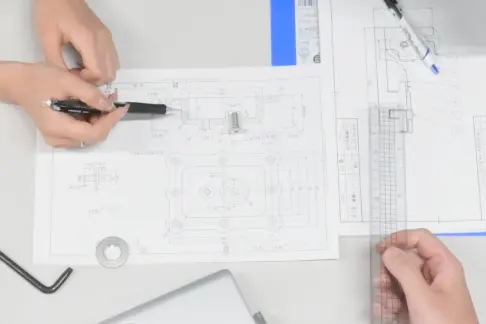解体分析エキスパート 第2回:ノートパソコンの解体分析
こんにちは!解体分析エキスパート(ティアダウンエキスパート Teardown Expert)の第2回目をお届けします。前回はデスクトップ型パソコンを解体し、使用されている締結部品について徹底的に分析しました。今回は予告通り、ノートパソコンを解体し、その構造と締結部品の使用実態について深掘りしていきます。
モバイル機器ならではの構造と特徴
ノートパソコンは、携帯性や省スペース性が求められる製品であるため、内部の設計もデスクトップ型とは大きく異なります。それに伴い、使用されている締結部品にもさまざまな工夫が施されていました。

今回解体したノートパソコンでは、半導体の固定に使われているものも含め、締結部品は合計で約230点確認できました。その注目ポイントは以下の通りです:
注目ポイント①:ゆるみ止め剤付き小ねじが70%
なんと、マイクロねじ・小ねじの約70%がゆるみ止め剤を塗布した小ねじでした。

これは、モバイル機器であるノートパソコンにとって、持ち運びや使用中の振動・衝撃によるねじの緩みを防ぐ重要な対策です。これにより、部品の安定性や製品寿命の向上が図られており、耐久性が求められるポータブル機器ならではの工夫が見て取れます。

注目ポイント②:インサートナット類の活用
さらに、35個のインサートナット類が使用されていました。

これは、アルミやプラスチックといった比較的柔らかい素材にしっかりとしたねじ山を作るために使われており、本体の軽さと強さのバランスを取る工夫が感じられます。
注目ポイント③:ねじサイズと素材の多様性
今回確認されたマイクロねじ・小ねじのサイズは、呼び径がM1.6~M3、長さが1.6mm~12mmでした。頭部はほとんどが十字穴で、一部にトルクスねじ(4本)も確認され、頭径は3mm~6.8mmでした。精密機器ならではのマイクロねじ・小型ねじが多用されていたのが特徴です。狭いスペースに多くの部品を効率よく配置するには、部品同士の干渉を避けつつ、確実な締結が求められます。

また、素材に関しては以下の通りです:
◇ プラスチックワッシャー:4個
◇とめわ(止め輪):7個
◇非磁性材(オーステナイト系ステンレス鋼):10個
◇その他は磁性材
といった構成でした。非磁性材の使用は、磁場の影響を避けるべき精密部品周辺で使用されており、細かな配慮が設計に反映されています。

注目ポイント④:表面処理と材料特性
締結部品の表面処理にも、ノートパソコンという精密機器ならではの工夫が見られました。
特に目立ったのは、黒染め処理されたマイクロねじ・小ねじが約50個使用されていた点です。黒染めは外観の統一に加え、軽度な防錆効果も期待できる処理であり、コストと機能のバランスに優れた選定といえます。

黒染め処理されたマイクロねじ・小ねじを確認できる
また、腐食に強いニッケルめっきが施された締結部品も複数確認されており、湿度や温度変化が想定される使用環境において、耐久性を確保する工夫がなされていることがわかりました。
基板内部で電気回路に異常が発生し、瞬間的に電流が大きくなる、いわゆるショートを引き起こす原因となるウィスカ(直径1~2μm、長さ10μm~数mmほどの非常に小さなヒゲ)に対しては、ニッケルめっきや銅めっきが用いられ、ウィスカの成長を抑制する対策も見られました。
さらに、インサートナット類においては、電気伝導性の高い真鍮製が主に使用されており、これは内部のアース接続や静電気対策を意識した素材選定と考えられます。軽量化だけでなく、電気的特性まで考慮した設計意図が垣間見えました。


解体結果と考察:締結部品最適化のヒント
前回のデスクトップ型に比べて、部品点数が倍近くに増えているにもかかわらず、それぞれに明確な目的と意図があることが印象的でした。

特に以下の改善提案が可能と考えられます:
●ゆるみ止めマイクロねじ・小ねじの標準化:種類を絞ることで在庫管理の簡素化と組立効率の向上が見込めます。
●サイズ統一の推進:ねじサイズをある程度統一することで、作業工数の削減と締結ミスの防止につながります。
まとめ
デスクトップ型パソコンは室内で使用されるため、比較的安価で表面処理された鉄製のねじが多く使用されていましたが、ポータブルなノートパソコンでは、耐食性を持つステンレス鋼製のねじも多く見られました。
ノートパソコンのように高密度・高精度な製品では、締結部品の選定や配置が、製品全体の性能や信頼性に直結します。解体分析を通じて得られた知見は、設計者にとっても、調達・品質管理担当者にとっても、貴重なヒントになると感じました。
次回予告:電子レンジの解体分析
次回は、家庭用電化製品の代表格「電子レンジ」を解体・分析します。高温部品や高電圧回路、可動部が組み合わさる複雑な構造の中で、どのような締結部品が使用されているのかを調査します。耐熱性や絶縁性、安全性を確保するための締結設計の工夫にも注目し、詳しくご紹介していきます。どうぞお楽しみに!